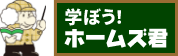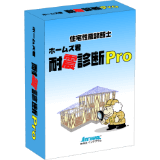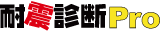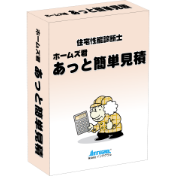地震被害調査 平成19年(2007年)能登半島地震
能登半島地震の被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
地震概要(気象庁速報値)
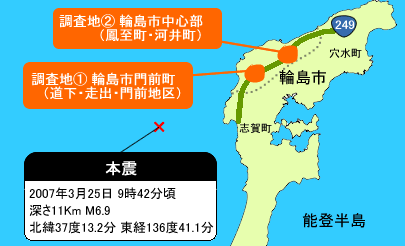
※震度5弱以上のもの
| (1)本震 | |
|---|---|
| 発生日時 | 2007(平成19)年3月25日 9時42分頃 |
| 震央 | 石川県能登沖 (北緯37.2度、東経136.8度、深さ11㎞) |
| 地震の規模 | (マグニチュード)6.9 |
| 各地の震度 |
|
| (2)余震(平成19年3月25日) | |
| 発生日時 | 2007(平成19)年3月25日 18時11分頃 |
| 地震の規模 | (マグニチュード)5.3 |
| (3)余震(平成19年3月26日) | |
| 発生日時 | 2007(平成19)年3月26日 14時46分頃 |
| 地震の規模 | (マグニチュード)4.8 |
| (4)余震(平成19年3月28日) | |
| 発生日時 | 2007(平成19)年3月28日 8時8分頃 |
| 地震の規模 | (マグニチュード)4.9 |
〔被害の状況〕
地震動は七尾市、輪島市、穴水町で震度6強、志賀町、中能登町、能登町で震度6弱が適用され、最大加速度は945ガルを記録し(防災科学技術研究所)、阪神大震災の818ガルを超える大きさとなった。
人的被害は死者1名、重軽傷336名。住家被害は全倒壊は593棟、半倒壊は1206棟(2007年5月14日 国土交通省調べ)となっている。
調査概要
石川県輪島市を中心に能登半島地震の調査を行いました。
調査にあたっては、主に木造住宅を中心に、地震による被害の状況の把握及びその特徴と被害を受けた原因の分析を目的としました。
今後、今回の調査を踏まえ、より詳細に木造住宅の被害要因の分析を行う予定です。
第1次調査(石川県輪島市)
第2次調査(石川県輪島市)
| 調査日 | 2007年3月30日(金)~2007年3月31日(土) |
|---|---|
| 調査地 | 石川県輪島市(門前町, 鳳至町) |
| 調査者 | 宇都野直弘、岩崎護、澤井博 |
建物倒壊分析マップ
能登半島地震調査報告(2007/04/02)
調査結果と考察
今回の地震による死亡者は一人、負傷者は三百人弱(2007/5/17時点:336人)—この数字を頭に置いた上で、輪島市門前町を訪れまず感じたこ とは、「不幸中の幸い」だった。住宅街の通りに入って初めに目に入ってきたのは、一階部分が完全に押しつぶされた家。もしこの中に人が取り残されていたら、まず命は無かっただろう。
街中には同じような被害の建物が多く見られる。中には一階も二階も全く原形をとどめていないものもあり、また倒れてこそいないものの大きく傾き、倒壊寸前の建物もあった。これで家屋倒壊による死亡者がいなかったのは、まさに不幸中の幸いと言える (死亡者一人は石灯籠の倒壊によるもの)。もし同じ地震が、多くの人が就寝中の時間帯に起きていたら、人的被害はさらに深刻なものになっていただろう。
改めて地震の恐ろしさを実感しつつ、被害にあった建物の傾向を考察してみる。
2004年改訂版「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に即した耐震診断法(一般診断法、精密診断法1)では、建物の耐震性には様々な条件が影響するが、特に大きく影響するものとして、次の1~6がある。
- 立地の地盤
- 建物重量(特に屋根重量)
- 壁(耐力壁、筋かい 等)の多さ、強さ
- 壁の配置バランス
- 柱頭柱脚の接合部
- 部材の劣化
今回大きな被害を受けた建物について1)~6)の観点から考えると、以下のような不利な条件が重なっていたことがわかる。
-
被害の特に大きかった門前町は地盤が軟弱な地域であった。
-
ほとんどの土蔵(非常に重い建物)は倒壊していた。
-
多くの建物の屋根はどっしりとした瓦屋根(葺土あり)であり、建物にかかる重量も相当なものと見える。(皮肉なことに、完全に倒壊した建物でも屋根瓦だけは比較的きれいな状態で残っていた)
-
ほとんどの建物は1981年以前に建てられた建物であり、壁量が不足していると思われる。
1981年の建築基準法改正の際に、建物に必要とされる壁量が大幅に引き上げられた。
そのため、それ以前の基準で建てられた建物のほとんどは現在の基準で判断すると壁量不足となる。 -
道路に面する部分(建物正面)がほぼ全面にわたって戸や窓(開口部)になっている建物(=壁の配置バランスが偏っている建物)が多いと言える。
-
多くの建物は建築時からかなりの年月が経過しており(築50年以上と思われる)、地震により壁が剥がれ落ちてむき出しになった箇所から見える部材はひどく劣化(蟻害、腐朽)していた。
これら大きな被害を受けた建物に対し、比較的新しい建物では、外壁の剥離や基礎のひびなどはあっても、大変形や倒壊といった致命的な被害を受けているものはほとんどなかった。
特に、門前町に建っていた竣工直後と思われる建物は外壁から基礎に至るまで、変形はもちろん傷一つなく、一見すると大地震にあったということが全く感じられないほどだった。
このように、建物の条件により、地震被害の大小がはっきりと分かれている。ただし、悪条件(開口部が多い、屋根が非常に重い)と思われる建物でも目立った被害がないものもあった。
いずれにしても、現在の耐震診断法の妥当性は確認できたと言えるだろう。
やはり、建物を地震の被害から守るためには、正しく耐震診断をし、一刻も早く耐震補強を行うことが重要であると再認識した。