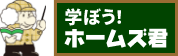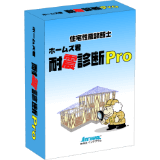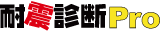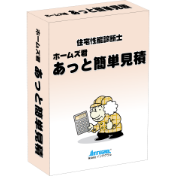地震被害調査 平成30年(2018年)北海道胆振東部地震
平成30年北海道胆振東部地震の被災地の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
地震概要※注1、注2
| 発生日時 | 平成30年9月6日 03:07 |
|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 (北緯 42.69 度、東経 142.01 度) (暫定値) |
| 規模 | マグニチュード 6.7 (暫定値) |
| 震源の深さ | 37km (暫定値) |
| 震度 |
|
被害状況※注2
住宅の被害
| 札幌市 | 厚真町 | 安平町 | むかわ町 | 北広島市 | 他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全壊 | 48 | 44 | 63 | 17 | 13 | 1 | 186 |
| 半壊 | 177 | 32 | 251 | 34 | 5 | 40 | 539 |
| 一部損壊 | 2,424 | 30 | 1,641 | 314 | 80 | 545 | 5,034 |
非住宅の被害
818棟 (札幌市19棟、厚真町129棟、安平町616棟、むかわ町50棟、他4棟)
調査概要※注3
震度7を観測し大規模な土砂崩れが発生した厚真町、震度6強を観測した安平町およびむかわ町、液状化が発生した札幌市清田区を調査した。主に木造住宅を中心に被害状況を調査し、その特徴や原因を分析した。
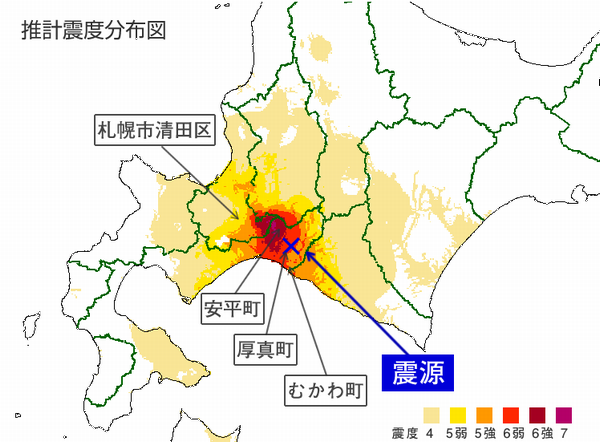
| 調査日 | 平成30年9月27日(木) |
|---|---|
| 調査地 | 厚真町、安平町、むかわ町、札幌市清田区 |
| 調査者 | 柳澤泰男(一級建築士・茨城県木造住宅耐震診断士) 落合小太郎 |
札幌市清田区
液状化が発生した区域の多くは、自治体や警察により立ち入り禁止とされており、詳細な調査は行えなかった。しかし、立ち入り可能な、比較的被害が小さく見える場所でさえも、住宅が傾いたり一部損壊するなど、液状化の被害の深刻さが確認できた。地震の揺れによると思われる被害は、比較的少ないように見受けられた。






安平町
地震の揺れによると思われる建物の被害が散見された。主に、古い建物や老朽化した建物の被害が大きかったように見受けられた。一方で、新耐震基準が施行された1981年以降と見られる比較的新しい建物は、揺れによる被害が比較的小さいように見受けられた。完全に倒壊している建物もいくつか見受けられ、取り壊しも進んでいた。他にも、外壁の損傷がある建物が多く見受けられた。







厚真町
大規模な土砂崩れが多発し、住宅や樹木が根こそぎ破壊された箇所が複数見受けられた。崩れた土砂を見ると、灰や砂のような土砂が多く見受けられ、土砂崩れの規模が大きくなった一因と考えられる。※注4 なお、震度7だったにも関わらず、揺れによるものと思われる建物の被害(倒壊、損傷、傾きなど)は、これまで震度7を観測した被災地に比べると、少ないように感じられた。








むかわ町
安平町と同様、地震の揺れによると思われる建物の被害が散見された。特に、町の中心となる通りに沿って、1階から傾いたり潰れて倒壊した建物が多く見受けられた。








まとめ
今回の被災地の特徴として、いずれの地域においても、土砂崩れや液状化など地盤の損傷による被害は極めて甚大だが、地震の揺れによる建物の被害は、震度の大きさに比べると少ないように見受けられた。しかし、建物の耐震性が全体として充分であると安易にみなすのは危険である。
地震の揺れによる被害が少なかった要因の一つとして、今回の地震動の主な周期が、木造建物の全壊・大破といった大きな被害と相関を持つ地震動の周期帯「1.0~2.0秒」であった地域が一部に限られていたためと推測される。※注1、注5
実際、今回の地震と同じく震度7を観測した2016年の熊本地震においては、周期「1.0~2.0秒」の地震動が卓越した結果、1981年の新耐震基準や住宅性能表示における耐震等級2を満たした建物の一部でも、倒壊する被害が確認されている。
土砂崩れはともかく、地震によって万一液状化が発生しても、揺れによって建物が破損をしなければ、中にいる人の生命はある程度守れる可能性が高くなると考えられる。
地震の揺れによる建物の被害を減らし、生命や財産を守るためにも、既存住宅であれば耐震診断・改修を可及的速やかに行い、新築住宅であれば、「最低限の安全基準」である建築基準法だけでなく、住宅性能表示における耐震等級3を確保したり、許容応力度計算などの構造計算を行って、建物の耐震性を高めなければいけないことを再認識した。
脚注
-
注1:出典:国立研究開発法人
建築研究所「平成 30年北海道胆振東部地震による建築物の被害に関する調査結果」(平成30年10月2日付)
https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/topics/2018/iburi01.pdf -
注2:出典:内閣府
「平成30年北海道胆振東部地震に係る被害状況等について」(平成30年9月27日18:00分現在)
http://www.bousai.go.jp/updates/h30jishin_hokkaido/pdf/300928_jishin_hokkaido_01.pdf -
注3:出典:気象庁
「推計震度分布図」
http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/suikei/201809060308_146/201809060308_146_1.html -
注4:出典:国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
現地調査報告その1「安平町、厚真町、苫小牧市における地震被害の概査報告」(平成30年9月13日付)
https://www.gsj.jp/hazards/earthquake/hokkaido2018/hokkaido2018-06.html
現地調査報告その2「厚真町における表層崩壊」(平成30年9月13日付)
https://www.gsj.jp/hazards/earthquake/hokkaido2018/hokkaido2018-07.html -
注5:出典:筑波大学 境有紀教授 (システム情報工学研究科 構造エネルギー工学専攻)
「北海道胆振東部地震で発生した地震動と被害調査速報」(平成30年9月18日付)
http://sakaiy.main.jp/hit.htm